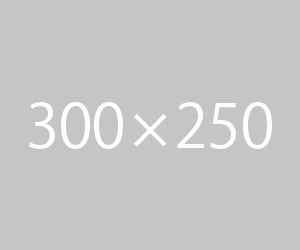目的のない進学は正解なのか?
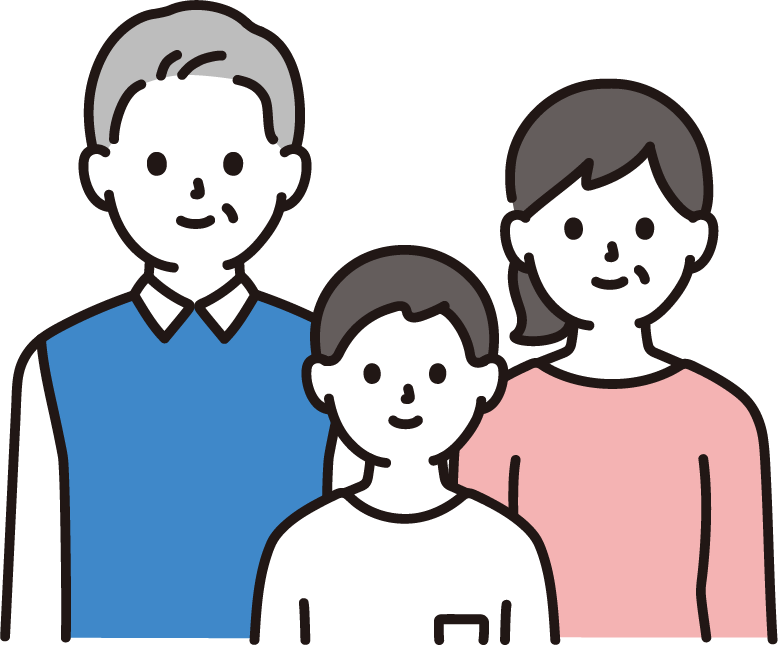
何の目的もないのに、大学に進学することは、
希望や目標を見つけるためだと、思っていませんか?
もし、
「それっておかしくない?』って
感じた人に、読んでほしいお話です。
日本の進学のスタイルは、アメリカの教育制度を真似ています。
日本の進学スタイルは、アメリカ型
日本の大学は1990年をさかいに、経営の効率化を目的に改革が進みました。
そのモデルとなったのが、アメリカ型の制度や手法でした。
シラバスという言葉が使われるようになったのも、
弁護士や裁判官になるための、司法試験が
法科大学院という形になったのも、アメリカのロースクールがモデルです。
大学進学に重きを置く、アメリカ
昔からアメリカには多くの移民が住んでいます。
アメリカに渡ってきた人がまず働く先として飲食、建設、清掃など、知識がなくてもできる仕事に就きました。
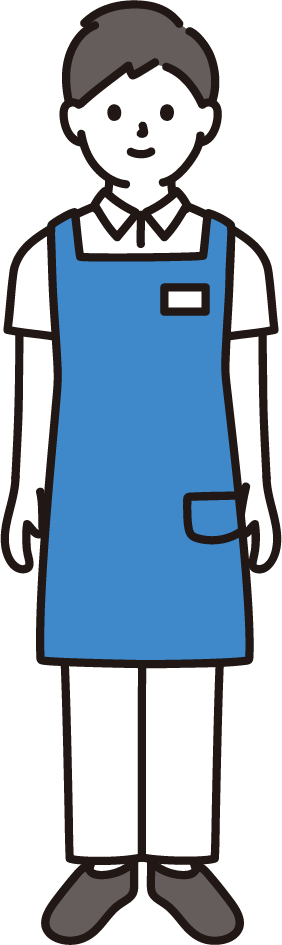
それがブルーカラーのイメージとして強く定着してきた背景があって
職業や身分について、我々日本人よりも、強い意識を持っています。
また終身雇用で成り立ってきた、日本と違い、雇用は安定しません。
会社の業績が悪くなると、解雇は当たり前の社会です。
解雇される人はブルーカラーの労働者が対象になることが多く、
大学で専門的な知識を得てから社会に出ようと、
ホワイトカラーな職業を志望する思考するベースが出来上がっています。
日本の進学スタイルは、このアメリカ型の進学を真似ているとしたら、
ちょっと、おかしな話ですよね。
お分かりかと思いますが、日本では、お酒や味噌を作る職人には、社会的な認知と尊敬の念がありますし、
大工や寿司職人として働く人を、社会的に差別する話しは聞きません。
ヨーロッパのいくつかの国では、技能職としての地位ができていて
ブルーカラーと言われる職業に就いている人でも社会的地位が保証され、収入も多いという国もあります。
ドイツのマイスター制度は有名な話ですし、

フランスのMOFなどは技能職の国家資格として、最高の栄誉されています。
日本でも技能オリンピックや作物の出来や料理の腕を競う大会がたくさんありますが、
あくまで「イベント」というレベルで、
社会的な保証や人材の育成や進路の1つにはなっていません。
日本の進学状況を見ても、
大学や専門学校に進学する人は全体の9割以上で、アメリカと同じ水準なのに対して、
ドイツでは70%、それも大学進学よりも
職業訓練制度を活用することを尊重されている訳です。
社会的不平等と階層意識の国際比較 東京大学社会科学研究所 石田宏氏
つまり日本の進学スタイルはアメリカ寄りで、
職業に対する意識や社会は、ヨーロッパに近いものがあるという、
いびつな構造が見えてくるのです。
最初のデータを元に、再度お話しすると、
進学85%の裏には、15%の就職が存在するという事実です。
この15%に舵を切った人の多くは、
きっと、このいびつな構造に疑問を抱き、将来を見据えた選択をした人が
少なからずいたのではないかと想像しているのです。